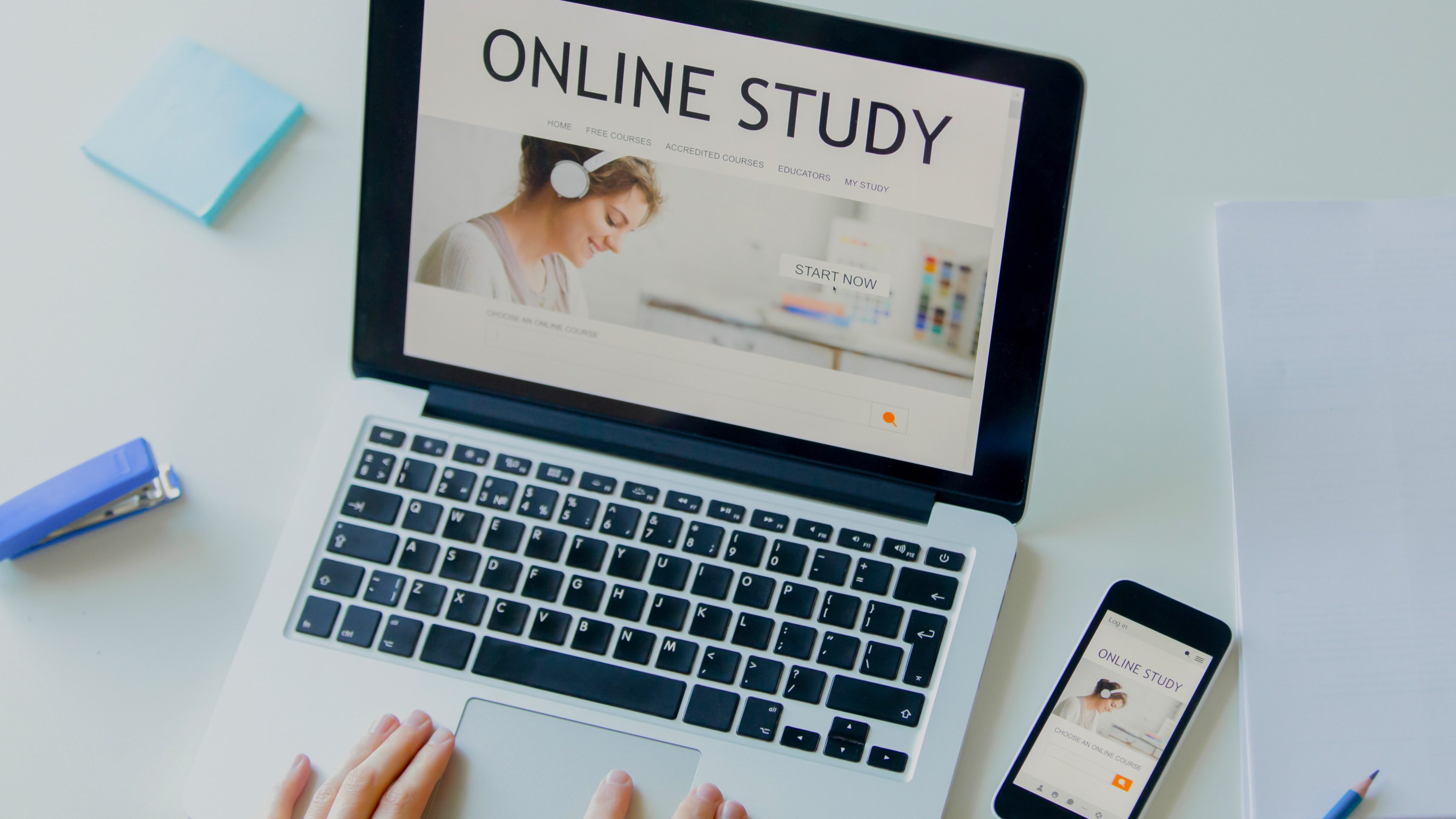新卒採用で「社員の本音と仕事の解像度」を最短で伝えられるのがインタビュー動画です。
本人の言葉がもつ説得力で効果的にターゲットに会社や仕事の魅力を伝えられるだけではなく、説明会や採用サイト、SNSまで横展開しやすい汎用性の高さもポイントです。
一方で、台本の丸暗記や質問設計の甘さは印象を平板にし、視聴維持率や志望度を下げかねません。成果を出すには、目的から逆算した構成と質問設計、現場運用、編集まで“伝わる型”を押さえることが不可欠です。
本記事では、採用映像を多数手がけてきた筆者が、制作のポイント(コツ)や、よくある失敗と対策までを実務目線で徹底解説します。
なぜ“インタビュー動画”が新卒採用に効くのか

新卒採用において、インタビュー動画を制作する企業が多いのには明確な理由があります。数多くの採用担当者の方の声から3つピックアップしました。
なぜ「インタビュー動画」が人気なのか?
インタビュー動画が人気な理由は大きく下記の3つです。
- 少ない予算でも制作可能である
- 短い期間で制作可能である
- コンテンツとして効果的である
1つずつ解説します。
少ない予算でも制作可能である
新卒採用インタビュー動画は、ミニマムな予算としては30万円ほどから検討可能であり、比較的安価に制作できるというのも特長の1つです。
もちろん、制作費によってクオリティは上下しますが要件設計次第で十分な品質を担保できます。このあたりは下記の記事で詳しく解説しているので、気になる方はご参考ください。
あわせて読みたい
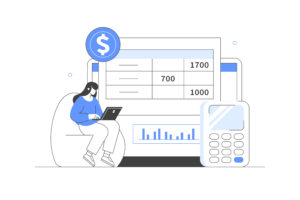
短い期間で制作可能である
通常の動画制作の場合2−3ヶ月程度かかることが多いですが、インタビュー動画であれば出演者・許諾・撮影日の確保が速やかに整えば、3週間程度での納品も可能です
また、制作期間が短いだけではなく、他の動画に比べると発注側の担当者の方の負担も少なく、動画制作が初めてでも安定したクオリティで納品されることが期待できる動画である点も大きなポイントでしょう。
インタビュー動画の制作期間については、下記で詳しく解説していますので、ぜひご参考ください。
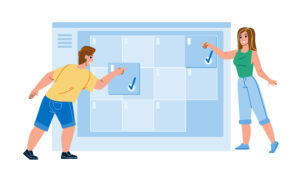
コンテンツとして効果的である
新卒採用の現場で、学生から支持される定番コンテンツが「先輩社員の声」です。採用サイトやパンフレットでも展開できますが、あえて“動画”で作る意味はどこにあるのでしょうか。
最大の理由は、インタビュー動画なら「本人の言葉を、本人の声と表情で」届けられること。声色や間、視線、ちょっとした笑みまで――テキストや静止画では伝わりにくい非言語情報が説得力を一段押し上げ、仕事のリアルやカルチャーの空気感まで想起させます。同じ内容を文章で読ませるより、動画のほうが圧倒的に“腹落ち”しやすいのです。
他社がどのような新卒向けインタビュー動画を活用しているかは、事例まとめもあわせてご覧ください。

新卒採用向けインタビュー動画制作のポイント

インタビュー動画を制作する際に、外せないポイントがいくつかあります。筆者がお客様に必ず伝えているのは下記の3つです。
・インタビュー動画の狙いの設定
・インタビュー動画の役割の設定
・インタビュー動画を含めた、学生へ提供する情報設計
1つずつ解説します。
インタビュー動画の狙いの設定
目的、と言い換えることもできますが「なぜ」「なんのために」インタビュー動画を制作するのか?を明確にする必要があります。
前述のメリットを満たすもの、というざっくりとしたものでもよいですが、特にかけられるコストが限られる場合には狙い・目的を絞り込み、限られた予算で狙い・目的を達成するための設計が必要になります。
例えば、インタビュー動画の狙い・目的が、
・学生に自社で活躍するイメージを持ってもらう
のように明確になるとインタビューでどのような質問をしてどのような言葉を引き出すべきかも明確になってきます。
インタビュー動画は比較的シンプルでコストを抑えやすい動画ではありますが、その狙い・目的によって「なにに、どこまでコストをかけるか」という判断も変わるため、この点を明確にする必要があります。
インタビュー動画の役割の設定
「狙い・目的」と並行して、動画に“何を担わせるか”という「役割」も定義しておく必要があります。ここが曖昧だと、撮るべきカットや台本、尺配分、CTA(次のアクション)設計までブレてしまいます。
例えば、狙いが「学生に自社で活躍するイメージを持ってもらう」なら、動画の役割は〈先輩社員の活躍を具体と感情の両面で伝える〉こと。仕事の一日の流れ、成果物、周囲との関わり、学びや成長実感といった要素を、本人の言葉と現場映像で重ねて“イメージ化”させます。
一方で、狙いに「志望度の向上」や「次の選考ステップへ進んでもらう」が含まれるなら、役割は変わります。たとえば、志望のボトルネック(配属の不安、成長機会、働き方など)を打ち消す情報を盛り込み、視聴直後に取ってほしい行動(説明会予約、エントリー、資料DL、関連記事閲覧)へ自然に導く導線とCTAを設計します。役割が変われば、必要な情報・画づくり・ナレーションのトーン・章立ても大きく変わる、ということです。
なお、1本の動画で全てを満たそうとすると、メッセージは薄まり、制作コストも膨らみがち。まずは役割を1〜2点に絞り、その他の目的は別フォーマット(FAQ記事、別動画、メールフォロー等)で補完する構成をおすすめします。最終的には、企画書の冒頭に「狙い」「役割」「成功指標(視聴後の行動)」を並べて合意しておくと、制作と運用のズレを最小化できます。
インタビュー動画を含めた、学生へ提供する情報設計
インタビュー動画を作るかどうかに関わらず、まずは「狙い・目的・役割」を明確にし、そのうえで視聴前後の学生の心理や行動を見立てた情報設計が不可欠です。
最低限押さえるべきは、
①視聴時点の学生の心情・状況、
②視聴後にどんな心境変化や理解が起きているか
の二点。さらに効果を最大化するなら、学生が動画に到達するまでの経路(検索・SNS・メール・採用サイト内導線など)と、視聴後に取ってほしい意思決定・次アクション(説明会予約、エントリー、関連記事の閲覧等)までを逆算して設計しましょう。
その想定に基づき、必要なコンテンツ(補足資料、先輩インタビュー、FAQ など)と適切な導線(CTA、関連リンク、フォーム連携)を用意することが、動画の効果を最大化する近道です。
新卒採用向けインタビュー動画の事例
では実際に、どんな会社がどのようなインタビュー動画を活用しているのでしょうか?いくつかの事例をご紹介します。
これらの事例については、こちらの記事で各動画の狙いと設計を詳しく解説しているのでぜひご参考ください。

あわせて読みたい
インタビュー動画の事例をもっと深堀り!
前段でご紹介した各動画の狙いなどについて、より深く解説しています。

新卒採用向けインタビュー動画の制作期間はどれくらい?
インタビュー動画を制作する際に必要な期間・スケジュールについて解説しています。
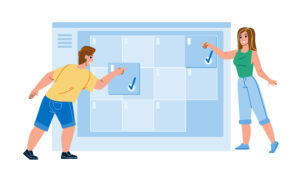
よくある質問
- 新卒向けインタビュー動画の制作費は?
-
30万〜150万円が目安。 最小構成(1日/1ロケ/2名/3–5分)で30〜60万、Bロール(インサート)充実・縦横短尺やモーショングラフィックス強化で100〜150万。
- 新卒向けインタビュー動画の制作期間の目安は?
-
標準3〜6週間、最短3週間。 前提は出演者・許諾・撮影日の早期確保。
- 新卒向けインタビュー動画の最適な尺と構成は?
-
3〜5分が基準。 導入15秒 → 職務の核 → やりがい/成長 → カルチャー → 応募前の一言 → CTA。SNS向け30〜60秒も併用。
- 新卒向けインタビュー動画の出演者を選ぶ基準は?
-
語りの安定感 × ロールモデル性。 カメラ前で自然に話せ、志望ターゲットが自分事化できる人。部署横断で男女/年次のバランスも。
最後に
繰り返しになりますが、インタビュー動画はシンプルにコストを抑えて制作できる一方で効果的なコンテンツであるため、優先度高く検討するべき採用向けの動画コンテンツです。
だからこそ、事前にしっかりと情報を整理し、狙いを定めることで動画の効果を最大化することをおすすめします。
もし、インタビュー動画の制作をご検討の際にはぜひお気軽にお声がけください。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。