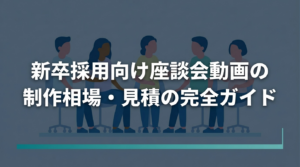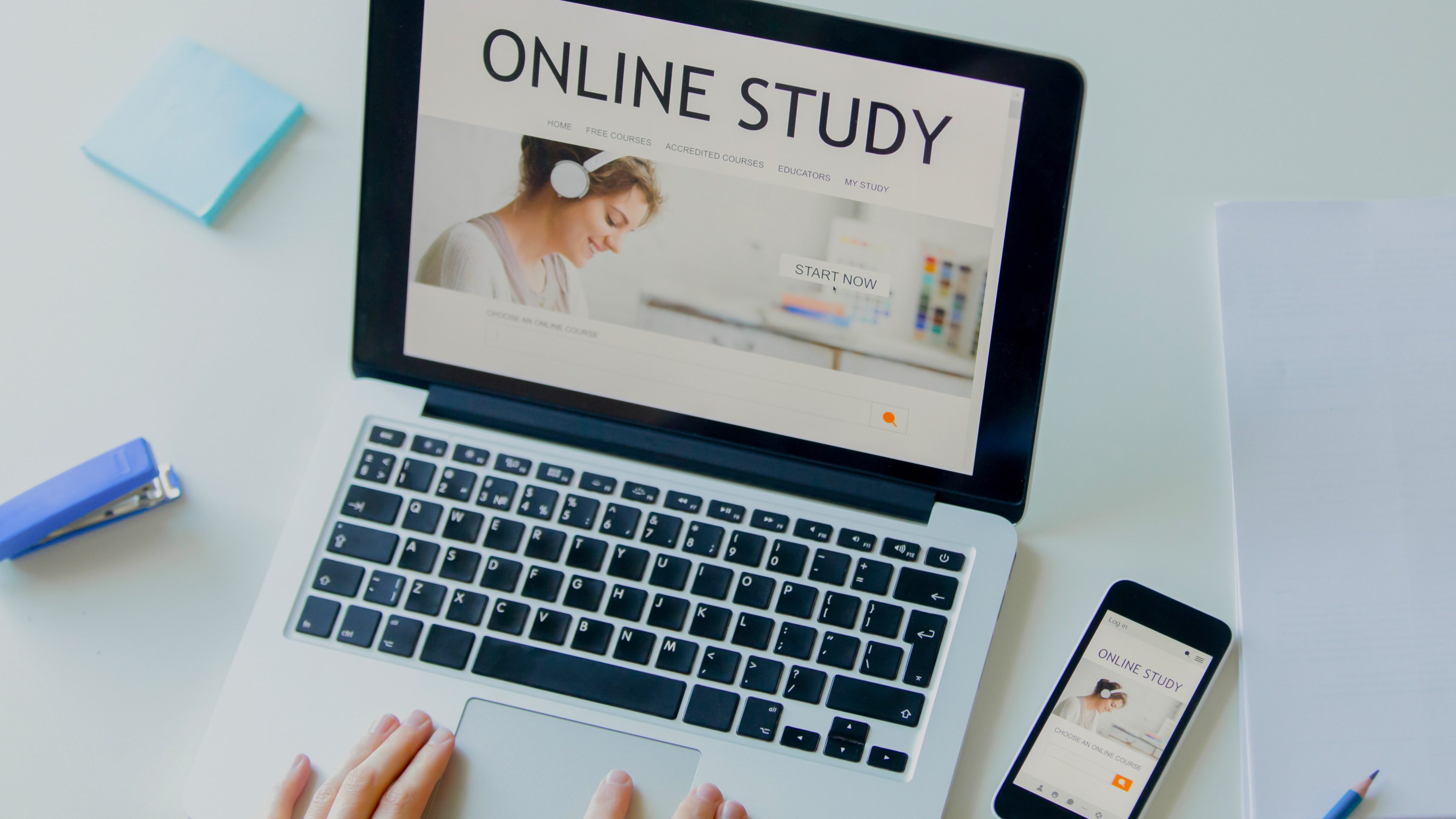新卒採用において、学生と企業が出会うきっかけは決して多くはありません。だからこそ、限られたタイミングで企業の雰囲気や働く人のリアルな声を届けられる「説明会動画」は、採用活動のなかでも重要な役割を果たします。
とはいえ、いざ動画を制作しようとすると「どれくらいの期間がかかるのか」「いつから動き始めるべきか」といったスケジュール面での不安を感じる方も多いのではないでしょうか。とくに、社内調整や学生側のスケジュール調整が必要になる採用関連の動画では、意外と余裕をもった進行が必要になることも少なくありません。
そこで本記事では、説明会動画を発注・制作する際に「いつまでに、何をしておくべきか」が明確になるよう、動画制作の流れと制作期間の目安について、実務経験に基づいて解説していきます。初めて動画を発注する方にも、計画を立てるうえでの参考になるはずです。
※本記事では、いわゆる「リアルタイムのライブ配信」ではなく、事前に収録・編集された説明会動画を前提に解説しています。
説明会動画が注目される背景

新卒採用の現場では、ここ数年でオンライン前提の広報・説明スタイルが一気に広まりました。従来は「説明会は会場に集まって開催するもの」という前提が強かったですが、今では オンライン配信の録画を再利用した動画 や リアル開催を代替する専用の説明会動画 を導入する企業が増えています。
なぜ説明会動画の活用が拡大しているのでしょうか。その理由は、企業・学生の双方にとって「効率性」が高いからだといえます。
企業側のメリット
企業にとっての利点は大きく、主に以下の4点が挙げられます。
- 全国の学生に同じ情報を一斉配信できる
- 移動や会場準備などの手間や費用を削減できる
- 「会社説明」の実施コストを抑えられる
- 担当者による説明のばらつきをなくし、均一な品質を保てる
さらに、説明会動画は比較的低予算で制作できることから、社内で承認を取りやすい点も大きな魅力です。制作費について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

学生側のメリット
学生にとっても説明会動画はメリットが多くあります。
- わざわざ会場に行かなくても視聴できる
- 自分の都合に合わせて好きな時間に閲覧できる
- 必要に応じて何度も見直せる
採用活動のトレンドを踏まえると、説明会動画を用意していないこと自体がマイナス印象につながる リスクも否めません。特に人気企業ほど積極的に導入しているため、エントリー数を増やしたい企業にとっては優先度の高い施策といえます。
動画ならではの強み
一方で、「動画だと集中して視聴してもらえないのでは?」と懸念される担当者もいます。確かにリアルな説明会と比べると、学生の姿勢は異なります。
しかし実際には、優秀な学生ほど複数の手段で情報収集しており、動画を軽視する傾向はほとんどありません。むしろ動画には、他の媒体にはない強みがあります。
例えば:
- 複雑な事業内容をアニメーションでわかりやすく表現できる
- 先輩社員のインタビューや働く様子を差し込み、臨場感を演出できる
- 実績や業績をグラフアニメーションで見せ、説得力を高められる
このように「動画だからこそ伝えられる表現」を取り入れることで、学生に強い印象を残すことが可能になります。
説明会動画の「制作スケジュール」とは?全体の流れを把握しよう
動画の制作スケジュールを考えるうえで、まず大切なのは「全体像」を把握しておくことです。いきなり「撮影は何月何日がいいか」といった細部の話に入ってしまうと、逆算できずにスケジュールが後ろ倒しになるケースも多くあります。
説明会動画に限らず、動画制作には大きく分けて 「企画」→「撮影」→「編集」→「納品」 という4つの工程があります。
各工程にかかる期間の目安
| 工程 | 主な内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 企画・構成設計 | 要件ヒアリング、企画案作成、絵コンテ・進行表の作成 | 約1〜2週間 |
| 撮影準備・撮影 | 撮影スケジュール調整、撮影実施(1日〜複数日) | 約1〜2週間 |
| 編集(仮編集〜本編集) | 編集→確認→修正対応 | 約2〜3週間 |
| 納品・エンコード | 納品形式での書き出し・データ納品 | 約数日 |
もちろん、上記はあくまで一般的な目安です。スケジュール調整に時間がかかる場合や、編集に複数回の修正が入る場合には、それぞれの工程が長引く可能性もあります。
「この時期までに動画を完成させたい」という納期が決まっている場合には、そこから逆算して準備を始めることが、スムーズな進行の第一歩です。
いつから準備を始めるべき?逆算で考える「最適な着手時期」
説明会動画は、就活の解禁時期やエントリー開始に合わせて公開されるケースが多いため、「いつから準備を始めればいいのか」はよく聞かれるポイントです。
一般的には 納品希望日の1.5〜2ヶ月前 には制作をスタートしておくのが安心です。たとえば「3月の会社説明会に間に合わせたい」のであれば、遅くとも1月中旬〜2月初旬には制作をスタートしたいところです。
制作会社の選定や予算調整などに時間が必要であれば、更に1−2ヶ月前には具体的な検討や制作会社との相談をしておく必要があります。
つまり、納品希望日の3−4ヶ月前には社内調整や制作会社選びをスタートさせるのが理想的だと言えます。
制作期間を短縮するために発注前にできること
タイトなスケジュールで進めたい場合でも、事前準備次第で制作期間を圧縮することは可能です。
- 構成の方向性を社内で固めておく
「どんなテーマで誰に話してもらうのか」など、基本方針をあらかじめ整理しておくと打ち合わせがスムーズになります。 - 調整役を一人決める
撮影日の調整や確認依頼などを一本化できる担当者を置くことで、無駄なやり取りを減らせます。 - 既存の資料や動画を共有する
採用パンフレットや過去の採用動画を事前に共有しておくと、制作側がイメージを掴みやすくなり、企画〜編集が効率化されます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 最短でどれくらいの期間で納品できますか?
-
条件が揃っていれば最短3週間程度での納品も可能です。ただし、修正回数や撮影条件によっては追加日数が必要になるケースもあります。
- Q. 複数パターンを制作する場合はどれくらい延びますか?
-
A. 撮影を同日にまとめればそこまで延びませんが、編集・修正工程が増えるため通常より+1〜2週間程度は見込むのが安心です。
- Q. 撮影が難しい場合、過去素材だけで作ることは可能ですか?
-
A. 可能です。既存のスライド・写真・動画素材を組み合わせて編集することで、短期間かつ低コストで制作できます。
あわせて読みたい
説明会動画の事例をもっと深堀り!
前段でご紹介した各動画の狙いなどについて、よい深く解説しています。

説明会動画の制作のポイント!
説明会動画を制作する際に外せないポイントを解説しています。

まとめ|説明会動画は“逆算”と“段取り”が成否を分ける
説明会動画は、新卒採用において学生の印象を左右する重要なコンテンツです。
制作自体は1.5〜2ヶ月程度で完了しますが、スケジュール調整や修正対応を考慮して逆算で準備を始めることが成功のカギになります。
初めて発注する場合や短納期が求められる場合でも、段取りをしっかりと組めば対応可能です。私たちも、最適なスケジュール設計からサポートしていますので、まずはお気軽にご相談ください。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。