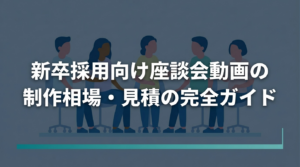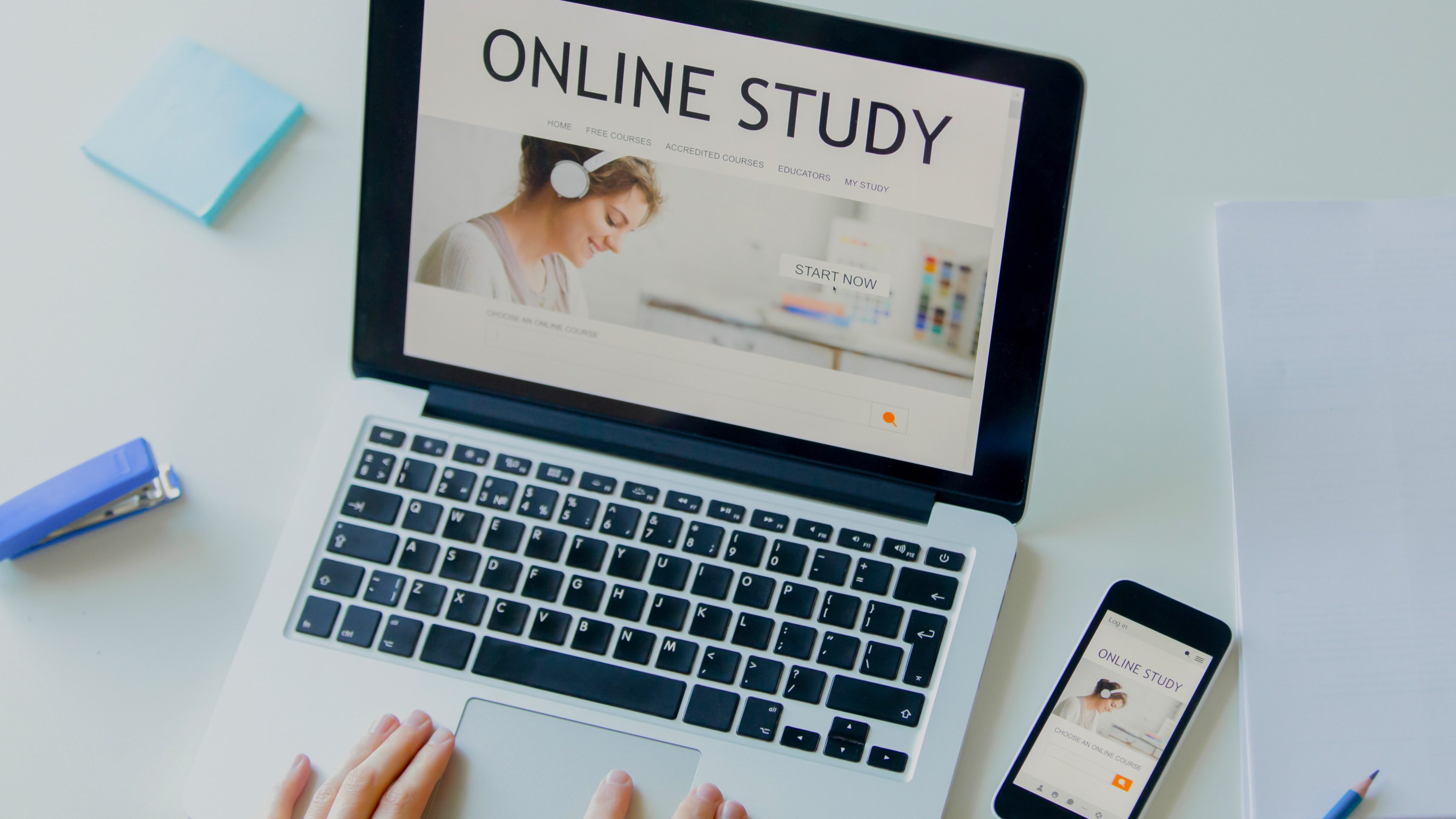ワークライフバランスは、内閣府のサイトでは「仕事と生活の調和」と約されており、ワークライフバランスが実現する社会とは、
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」
https://wwwa.cao.go.jp/wlb/towa/definition.html
とされており、あくまでも生き方として個々人にとって幸せで多様な選択ができることを目指していることがわかります。
一方で採用シーンにおいては「休みを取りやすい」「産休、育休などの制度が使いやすい」など仕事を「休むこと」にフォーカスされていることが多く、求職者側からは積極的に質問しづらい部分でもあります。
そのため、採用サイトなどを通じて自社の取り組みについて積極的に情報を開示している企業は多くありますが、動画を活用しているケースはまだ多くありません。
本記事ではそんな「ワークライフバランス」について会社のスタンスや考え方を求職者に伝えるツールとして、採用動画が有効である理由を、制作のポイント共にお伝えします。
採用動画についてよくある質問
- 採用動画の制作費はどれくらい?
-
制作する内容によって大きく変動しますが、概ね50万円〜200万円程度の制作予算で制作されるケースが多いです。
- 採用動画の制作期間はどれくらい?
-
制作する内容によって大きく変動しますが、概ね2ヶ月程度を想定しておくと良いでしょう。
- 採用動画の活用方法にはどのような方法がある?
-
採用サイトへの掲載、説明会での放映、YoutubeチャンネルやInstagramへの投稿など目的によって様々です。
ワークライフバランスを採用動画で伝える3つのメリット
ワークライフバランスの考え方やプライベートを充実してもらうために会社側でできることなどは、採用サイトなどを通して伝えることもできますが、動画であればそこにどのようなメリットが加わるでしょうか。
筆者が考える、採用動画で伝えるメリットは下記の3つです。
- より強い説得力
- 空気感や雰囲気を含めたリアルを伝えられる
- ワークライフバランスに注力しているという姿勢を示すことができる
1つずつ説明します。
①より強い説得力
記事の冒頭でも触れたように、採用シーンにおける「ワークライフバランス」は基本的には「どれくらい残業が必要になるか」「休みは取りやすいか」など仕事を休むことを意味していることが多く、求職者側からは積極的に質問しづらい部分です。
そのため、採用サイトなどを通じて自社の取り組みについて積極的に情報を開示している企業は多くありますが、動画を活用しているケースはまだ多くありません。
動画でワークライフバランスを訴求するメリットは、実際にそれを実現してる社員の方に語ってもらうことで「自社のワークライフバランスの実現が絵に描いた餅ではない」ことを示すことができることです。
インタビューなどで語ってもらうことによる説得力は、テキストや写真で構成した記事などで発信することとは比較にならないほどの説得力を持つのです。
空気感や雰囲気を含めたリアルを伝えられる
ワークライフバランスを実現するための、各種制度の使いやすさや働きやすさなどはそれを活かしてワークライフバランスを実現している人だけではなく周りの協力があってこそのものです。
そのため、普段働く職場がどのような雰囲気であるかも非常に重要な要素の1つとなります。
そして、それを伝えられることも動画の1つのメリットです。
もしインタビューなどで、社員の方にワークライフバランスについて語ってもらう場合には会議室だけ完結するのではなく、普段働いている様子なども撮影することでできるだけ社内の様子を見せることで「雰囲気」「空気感」も伝えるようにすると、より効果的な動画に仕上げることができるでしょう。
ワークライフバランスに注力しているという姿勢を示すことができる
まだまだ「ワークライフバランス」について伝えるために動画を制作・活用している企業が多くないからこそ、動画で発信することそれ自体が価値になり得ます。
採用コンテンツにどこまでお金をかけられるかや、優先順位などを考えると必ずしも優先度の高いコンテンツにはならないかもしれませんが、自社の特徴の1つとして「ワークライフバランス」を挙げることができるのであれば、検討するべきでしょう。
採用向けのワークライフバランス動画の制作のポイント
採用向けのワークライフバランス動画制作において、特に気をつけなければならないのは下記の4点です。
- 目的を明確にする
- ターゲットを明確にする
- 明確なコール・トゥ・アクションを設定する
具体的にどのようなポイントを抑えるべきか、1つずつ解説します。
目的を明確にする
すごく当たり前のことなのですが、意外と見落とされがちです。
「なんとなくカッコいい動画」「とりあえずインタビュー動画を制作しようと思ってます」とかだと、あまり意味のない動画が出来上がってしまいます。本当にもったいないです。
ちなみに、ここでいう「目的」は「エントリー数を増やす」とか「歩留まりを上げる」とかだと動画クリエイティブに落とし込むには少し抽象的です。
しっかりと役割を果たすことが期待できる動画を制作するためには、上記の「目的」に2〜3回ほど「WHY」をぶつけてみて下さい。
- なぜ歩留まりが低いのか?→面接での印象が良くない?会社や仕事の説明が分かりづらい?
- なぜ会社や仕事の説明が理解されないのか?→説明の仕方が悪い?内容が複雑でわかりにくい?
という感じで、ある程度のところまで深ぼったり要素分解しながら「動画の目的」を明確にしましょう。
ターゲットを明確にする
すごくすごく当たり前のことですが、これも見落とされがち…というか動画を制作するにあたっては少し解像度が荒い状態であることが多いです。
例えば、採用ターゲットは「法人営業職の経験者」だとして、動画のターゲットもそのままでよいのか?もう少し絞ったほうがいいのか?あるいは、広げたほうがいいのか?という部分を検討しきれていないケースがあります。
- 採用ターゲットは「法人営業職の経験者」
- 動画を制作するのは、〇〇〇〇という目的で、動画には〇〇〇〇という役割を担わせたい。
- そうすると、動画のターゲットは「法人営業職の経験者」かつ「どちらかというと、〇〇〇〇タイプ」というように絞り込まれるのか、もしくは「過去にスポーツなどに打ち込んだ経験のある人」というように少し広げるのか。
…という感じです。
前述の「目的」と紐づくため、ターゲットのことだけを考えても答えはでません。もしこの記事を読んで「あ…」と思った方は目的と合わせてどのようなアプローチが最適であるかについて、もう一度考えてみてはいかがでしょうか。
明確なコール・トゥ・アクションを設定する
「行動喚起」と訳され、デジタルマーケティングの世界ではユーザーに「次に起こしてほしい行動」を誘導することを指します。
つまり、動画を視聴したあとの行動としてどのような行動を期待するのか、そしてそのためにどのような気持ち・感情になって貰う必要があるのかを明確にしましょう、ということです。
当然ですが、やはりこの点についても目的との紐づきがあり、目的の解像度が低いとターゲットやコール・トゥ・アクションも同じように解像度が低い可能性が高いです。
もし、動画制作を具体的に検討しているようでしたら、まずはこれらのポイントを整理することから始めてみましょう。
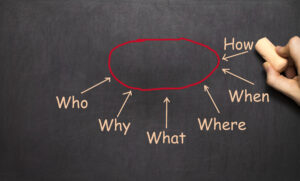
採用向けワークライフバランス動画の事例
【JFEエンジニアリング】 Work Life Balance~ワークライフバランス~
【DTC x Tech採用】Work life Balance コンサル業界で自分らしく働く|デロイト トーマツ コンサルティング
ワーク・ライフ・バランス~兵庫県教員採用~
本記事の作成にあたって、ワークライフバランスを訴求した動画をいくつも視聴しましたが、「不自然なインタビュー」「言わされ感のあるインタビュー」「明らかに台本を読んでいる」というような動画が多数ありました。
率直にお伝えすると、上記のような動画であれば制作しないほうが良いです。動画は訴求力の強いツールである一方で最低限のクオリティを実現できてないものは視聴者にネガティブな印象を与えてしまいます。
今回ご紹介した事例は上記のような部分をクリアした素晴らしいものなので、ぜひご参考ください。
動画制作の外注に失敗しないための4つのコツ
動画制作を外注した経験のある人の中には、なんらかの理由で「失敗した」「上手くいかなかった」と感じている方がいます。筆者も制作会社の営業として担当したお客様からそのような「以前お願いした会社で上手くいかず…」という相談を受けたことが何度かあります。
詳細は下記の記事にまとめていますが、ここでは失敗しないために重要な4つのポイントをご紹介します。

適切な制作会社を選ぶ
「それができれば苦労しない」と言われてしまいそうですが、やはりこの点は重要です。
ここで端的にお伝えしたいのは、「信頼できる営業担当者を選ぶ」という視点をもってみることです。
筆者が動画制作に携わり始めた10年ほど前とくらべると動画制作会社は格段に増えました。そしてどの会社も甲乙つけがたいほど豊富な制作実績を持っています。(弊社はまだ会社としての実績は少ないですが…)
その中で何をポイントに選ぶか?の1つのポイントが上記の「信頼できる営業担当者を選ぶ」という視点です。
詳しくは下記の記事にまとめていますが、端的にお伝えすると、

- 優秀な営業担当は、優秀なプロデューサー、優秀なクリエイターをアサインできる
- 優秀な営業担当は、無用なトラブルを避けてくれる
- 優秀な営業担当は、コミュニケーションがスムーズ
という3点です。「絶対この会社がいい!」と思える会社が見つからず悩むことがあればぜひ参考にしてみてください。
そしてもし悩むようであれば、ぜひ筆者にもご相談ください。
スケジュールに余裕を持つ
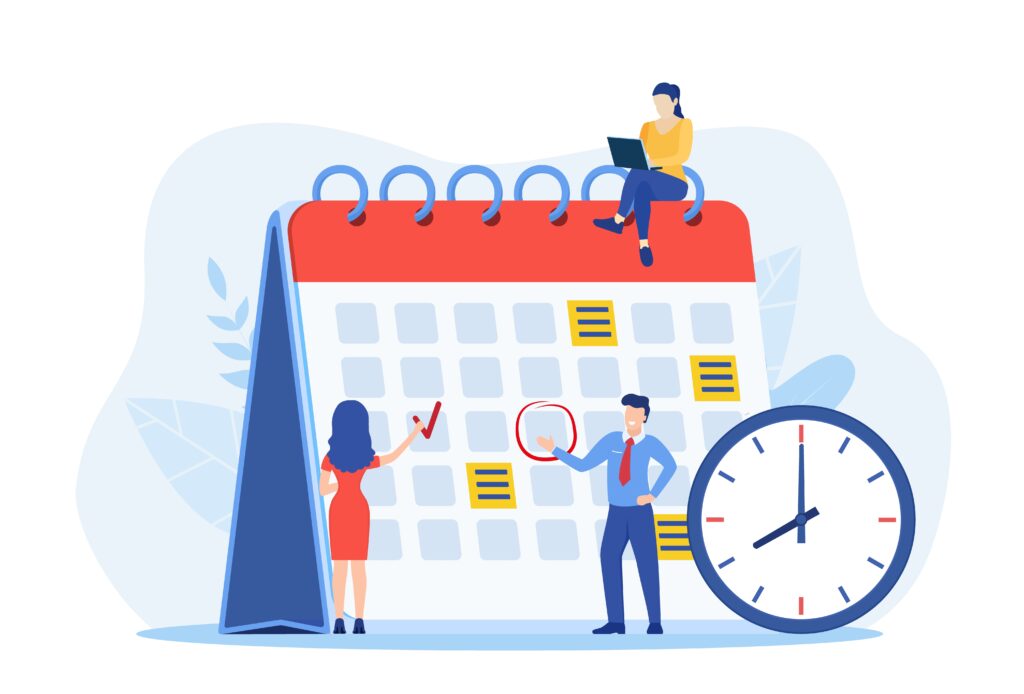
基本的なことではありますが、何らかの理由で急いで制作を進めなければならないケースもあります。そのような場合、
- 人的なリソースを確保するために通常スケジュールでの進行よりもお金がかかる
- 急ぐ分、準備・確認に通常より時間を割くことができず何らかのトラブルが起きる可能性が高くなる
…というリスクがあります。
会社によっては、短納期でも費用を抑えて制作してくれる会社もあるかもしれませんがそれでもスケジュールを短縮するということは、どこかでなにかを犠牲にせざるを得ません。
もちろん、通常スケジュールよりもトラブルが起きる可能性が高まるというだけで、「必ずトラブルになる」「失敗する」わけではありません。制作に慣れているプロが進行する以上、トラブルの種は極力排除し最大限問題なく進行できるよう尽力することは間違いありません。
ただ、それでも想定外のトラブルに見舞われることもあるのが動画をはじめ、クリエイティブ制作の現場です。
だからこそ、できる限りスケジュールには余裕を持つことを強くおすすめします。
制作内容によって変動しますが、インタビュー動画であれば、最低1.5ヶ月。できれば2ヶ月ほど制作スケジュールが確保できると良いでしょう。
上記はあくまでも「制作期間」なので、制作会社を選んだり正式に発注するまでのリードタイムがどれくらい必要になるかについては、自社の稟議や予算申請のフローについて事前に把握しておく必要があります。
完成イメージをできるだけ具体的にする
いざ、動画制作をスタートする際には制作会社側からどのような動画が完成する予定であるかは絵コンテやシナリオなどの資料を用いて説明があるはずです。
動画制作に慣れていれば、そのような資料で具体的なイメージを持つことができますが、初めての場合にはそれでもイメージが難しいこともあるでしょう。
そのような場合には、遠慮なく制作会社側に質問してイメージの具体化に努めましょう。
制作過程で完成イメージの認識の相違などのズレが生じてしまうと、軌道修正には時間とコストがかかってしまいます。
社内調整を怠らない
発注側の企業の担当者の方の役割の1つが、自社内のステークホルダーとの共通認識の形成です。
- こんな目的でこんな動画を制作します。
- これが完成イメージです。
- いつころ完成良い体です。
- このタイミングでシナリオや動画を確認して、いつまでにフィードバックしなければなりません
…などなど、動画制作の背景や前提、クリエイティブイメージ、スケジュールなどについて関係者としっかりと「握る」ことができていないと、後になって「どんでん返し」が起きることは珍しいことではありません。
特に、動画制作について最終的なOKを出せる決裁権者とのすり合わせは重要です。
最後に
いかがでしたでしょうか。筆者個人としては、ワークライフバランスのような人によって求めるものが異なる、少しふわっとした部分を訴求するのであれば、座談会形式のようにして複数の視点から自社のワークライフバランスについて語ってもらうような形式がマッチしやすいのではないかと考えました。
もし、ワークライフバランス動画を制作する際にはぜひご相談ください。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。