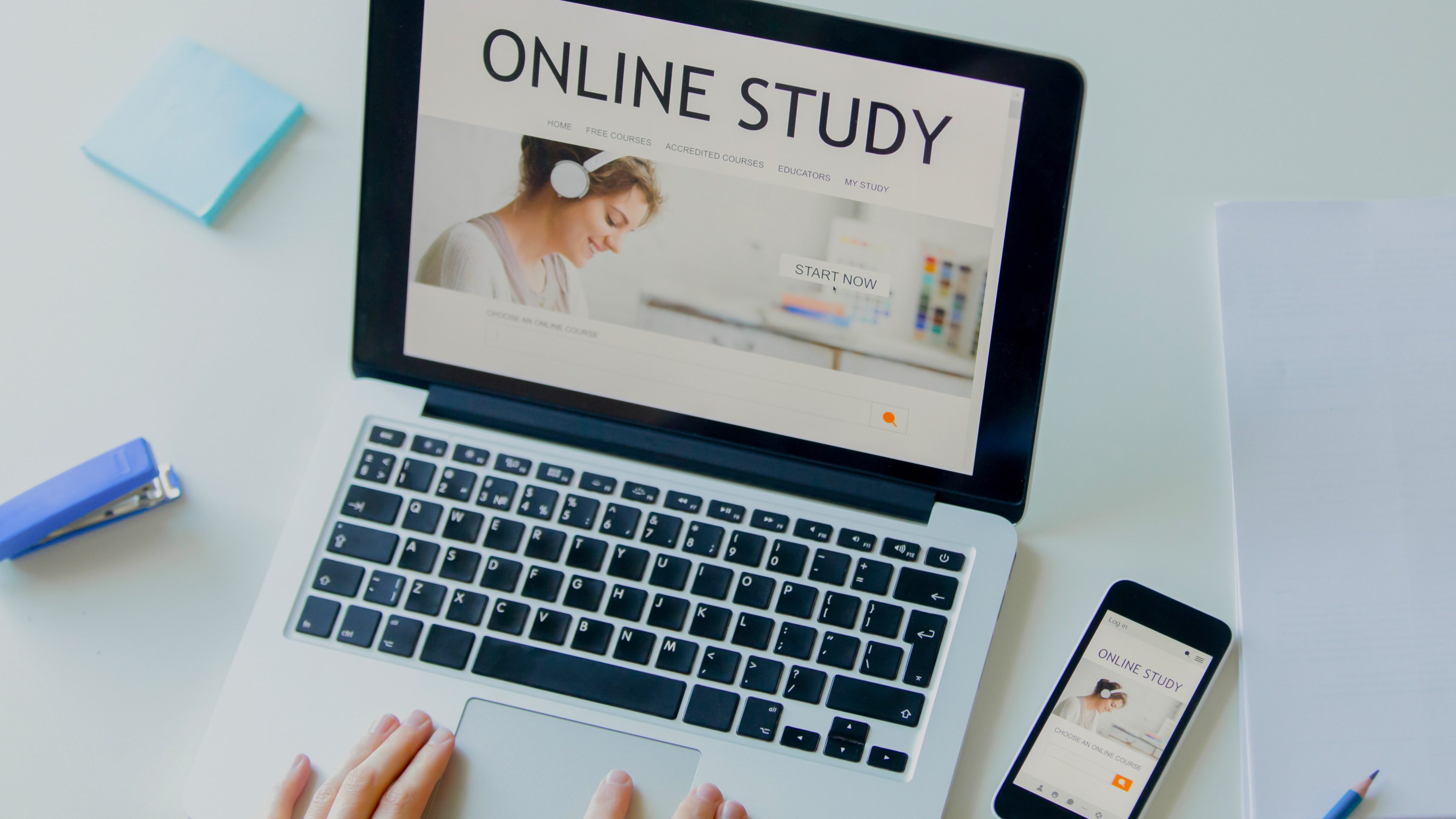展示会で動画を活用する企業が増えています。
音声を出せない会場でも視覚的に情報を伝えられ、ブースの賑やかしや空気づくりにも一役買ってくれる存在です。
ただし、「とりあえず動画を流す」だけでは、“なんとなく目立つ”に留まりがちで、狙った成果にはつながらないことも。
せっかくコストをかけて展示会に出展するからこそ、
足を止めてもらい、興味を引き、記憶に残る動画を作れるかどうかが、展示会活用の成功を大きく左右します。
この記事では、展示会で成果を出すための動画制作ノウハウを、実例や制作現場の視点からわかりやすく解説します。
筆者のプロフィール
まず、この記事を読んでいただくにあたって「誰が何を書いているのか?」も非常に重要な要素になると思いますので、簡単に私のプロフィールをまとめています。

【株式会社case 代表取締役/動画制作プロデューサー:加藤智史】
新卒で入社した動画制作会社で広告・マーケティング・採用・人材研修など約400本の動画制作に携わる。その後、TVCMなどの制作を行う、大手制作会社にアカウントエグゼクティブとしてジョイン。数千万円規模のプロモーション案件に携わり、動画にとどまらないクリエイティブ制作やプロジェクトマネジメントを経験。現在は本メディアの運営を通じた企業動画の受託制作や、動画制作会社の営業支援などを行う。
動画制作会社(予算数十万円〜数百万円)での営業兼プロデューサーとしての役割を中心に、広告代理店(予算数百万円〜数千万円)でのアカウント(クライアントと社内クリエイティブチームの窓口、PM業務を担当する役割
なども経験しているため、比較的高い説得力で本記事をお届けできるのではないかと考えています。
1. 展示会動画に求められる3つの役割

展示会で動画を活用するなら、以下の3つの役割を意識することが重要です。
- 足を止める(会話のきっかけをつくる)
- 何のブースかを一目で伝える(情報伝達)
- 記憶に残る印象を与える(ブランディング)
この章では、それぞれの役割を果たすためにどのような工夫が必要なのかを、プロの視点で解説していきます。
1. 足を止め、会話につなげる(最初の接点づくり)
展示会の来場者は、限られた時間の中で数十、数百というブースを見て回ります。そんな中で動画に求められる最初の役割は、「立ち止まってもらい、会話の糸口を生み出すこと」です。
単に派手な映像や賑やかなBGMを流すだけでは、“賑やかし”で終わってしまいます。
重要なのは、ターゲットが気になる情報や思わず反応したくなるフック・きっかけを動画の中に盛り込むこと。
たとえば──
- 「業界の○○、今こんな課題ありませんか?」
- 「来場者限定で、○○の事例資料を配布中」
- 「“3分で分かる○○”今すぐご紹介します」
といった、ターゲットにとって“知りたい情報”と“動機づけ”が重なるメッセージは非常に効果的です。
このように、興味関心を刺激し、「確かにこういう〇〇あるな」「もう少し詳しく聞いてみたい」と思わせることで、動画が営業スタッフとの接点を自然に生み出す装置になります。
展示会の現場では、動画が“静かな営業トーク”として機能しているかが成果の分かれ道になります。
2. 何のブースかを一目で伝える(情報伝達)
展示会では、動画の“最初から最後まで”をじっくり見る人は多くありません。むしろ、通りすがりに一瞬だけ視界に入るくらいが大半です。
だからこそ重要なのが、**「いつ・どのタイミングで見ても、何の動画かわかる」**という設計です。
たとえば──
- 冒頭だけでなく、常に会社名や製品名が画面に出ている
- ターゲットや課題が、映像内のテロップや図解で繰り返し表示される
- アイキャッチに「○○で困っていませんか?」といった問いを挟む
このように、断片的にしか見られないことを前提に、「誰向けに」「何を扱っている会社か」を視覚的・反復的に伝える設計が不可欠です。
展示会の現場では、「伝わること」が“次の会話”を生む第一歩となります。
3. 記憶に残る印象づけをする(ブランディング)
展示会が終わってからも印象が残っているかどうかは、今後の商談化や資料請求などの行動につながる重要な分岐点です。
動画は、短時間で感情に訴えることができる強力なツール。だからこそ、単なる情報伝達ではなく、「世界観」や「価値観」まで伝える表現が求められます。
たとえば──
- 一貫したカラー設計やモーショングラフィックで記憶に残す
- 自社のビジョンや“らしさ”をストーリー仕立てで語る
- 印象的な言葉やキービジュアルを繰り返す
単なるスペックやサービス紹介だけではなく、“印象に残る体験”としての動画設計を行うことで、展示会後の名刺フォルダの中でも「あの動画の会社だ」と思い出してもらえる確率が高まります。
2. 展示会向け動画の構成・演出で押さえるべきポイント
展示会動画は、Web用動画や営業資料としての動画と違い、「人の流れの中で、無数の視覚情報と競合する環境」で再生されます。だからこそ、映像構成や演出の工夫がそのまま成果につながります。以下の3点を意識しましょう。
1. “無音再生”でも伝わる設計にする
展示会場では音声が流れていない、もしくはBGMがかき消されることが多いため、映像とテロップだけで内容が伝わる構成が重要です。
- ナレーションに頼らず、テロップで要点を伝える
- 文字は大きく・少なめに(1画面に10文字以内が目安)
- アイコンやイラストで視覚的に伝わる工夫を
2. “視覚的な区切り”で注目を引き続ける
展示会動画は、途中から見られるのが前提です。常にどのタイミングで目に入っても興味を惹き、「何についての動画なのか理解しやすいことをを意識しましょう。
- 常に動画のタイトルや製品・サービスの特徴を動画に表示する
- ターゲットの興味をひきやすい課題やキーワードを散りばめる
- テキスト、音声、アニメーションなど各要素で伝える情報を分ける
…など、展示会動画でなくても重要なポイントではありますが、展示会動画の場合にはより強く意識する必要があります。
3. “一言フレーズ”で記憶に残す
すれ違いざまに見られる動画では、ひとことキャッチコピーのような訴求が大きな力を持ちます。
- 例:「◯◯業界の人事課題、動画で解決できます」
- 例:「業務効率、3分で体験してください」
一貫したメッセージを冒頭・中盤・最後に繰り返し配置することで、記憶への残りやすさが格段に上がります。
3. 展示会動画でよくある失敗と、避けるためのポイント
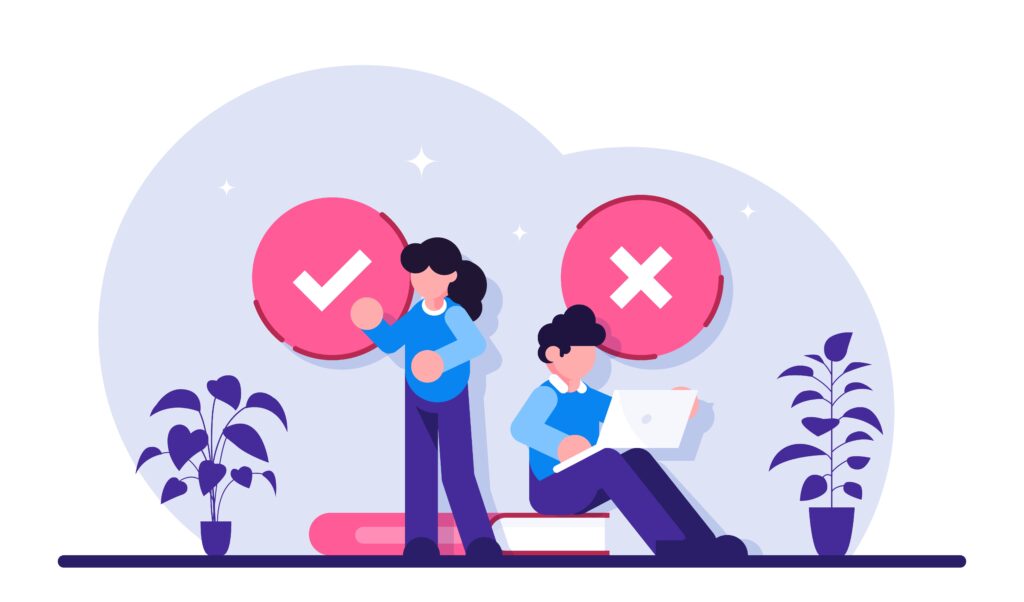
展示会に向けて動画を用意したものの、「なんとなく流して終わってしまった」「効果があったのかよくわからない」という声は少なくありません。ここでは、よくある失敗例とその改善策を紹介します。
失敗例①:社内紹介や沿革など“内向き”の内容を流してしまう
ありがちなのが、会社紹介や沿革、社員のインタビューなど、来場者にとっては関心が薄い“内向き”のコンテンツをそのまま展示会で流してしまうケースです。既存のアセットを活用するのはコスト面では重要ですが、あまりにも出展内容と関連が薄いと、来場者に「自分には関係のないこと」だと判断されてしまう可能性があります。
▶ 改善ポイント:
出展目的に直結した「ターゲットが知りたい情報」に特化する、もしくは、持っている動画が関連の薄いものであれば思い切って「動画は使わない」という判断も重要です。
失敗例②:情報を詰め込みすぎて、結局何も伝わらない
複数の製品やサービス、技術情報を“全部伝えよう”として、1本の動画に情報を盛り込みすぎるケースも失敗につながります。結果、印象が薄くなり記憶にも残りません。
▶ 改善ポイント:
あえて伝える情報を絞るのがポイント。1本に1テーマと割り切って、「一番伝えたいこと」に集中しましょう。
必要に応じて複数本の短尺動画を用意するのも有効です。
失敗例③:会場の環境を想定していない
制作時には気づきにくいのが、音が聞こえづらい・照明で画面が見えにくい・会場の動線と画面の向きが合っていないといった物理的なミスマッチです。
▶ 改善ポイント:
- 無音再生でも意味が通じるテロップ設計に
- 画面の明るさや配色に注意して“視認性”を確保
- 展示会ブースの設計段階で動画の配置や導線も一緒に考える
④ モニターの位置が見落とされている
ブース装飾にこだわるあまり、動画を流すモニターの位置が軽視されてしまうケースも少なくありません。来場者の視線に入らなければ、どんなに良い動画でも再生していないのと同じです。
▶ 改善ポイント
- 通路からの視認性が高い位置にモニターを配置する
- 動線上、立ち止まりやすい場所に動画を置く
- 小型モニターよりも大型ディスプレイの方が“目に入る”確率は高くなる
装飾や什器のレイアウトを決める段階で、「動画を見てもらう導線」も設計に組み込むことが重要です。
4. 展示会動画を制作会社に依頼する際のチェックポイント
展示会動画は、ただ「かっこいい映像」を作れば良いわけではありません。来場者の視線や行動、ブース内の導線、説明担当者との連携までを考えた設計が求められます。
そのため、制作会社を選ぶ際にも「映像のスキル」だけでなく、展示会というシーンに合った提案ができるかどうかを見極めることが大切です。
以下、依頼前に確認しておきたいチェックポイントを紹介します。
✔ 展示会での活用を想定した提案ができるか?
たとえば…
- 無音再生を前提とした構成・デザイン設計がされているか?
- 会場での視認性や導線まで考慮した内容になっているか?
- ターゲットに刺さる情報の優先順位をつけてくれているか?
→ 撮影・編集の技術以上に、「展示会という特殊な環境で機能する動画」を意識できているかが重要です。
✔ ターゲット理解に基づいた構成提案があるか?
ただスペックやサービス説明を並べるのではなく、
- 誰に向けて、どんな課題をどう解決するのか?
- 競合との違いや、自社ならではの強みはどこか?
といった**「構成の軸」を設計してくれるか**を確認しましょう。
→ 展示会で成果を出す動画は、“発信側の言いたいこと”ではなく“来場者の知りたいこと”に寄り添っている必要があります。
✔ 納期・スケジュールの余白があるか?
展示会の準備はブース設営や資料制作など、他の業務と並行して進みます。
→ スケジュールに修正や社内確認のための余白を見込んでいるか?
→ トラブル時の対応力や柔軟性があるか?
も事前に確認しておきたいポイントです。
✔ 撮影・編集など、各工程のクオリティが担保されているか?
「展示会だから動画のクオリティはそこそこで良い」と思われがちですが、視覚的に印象を与えるための編集スキルや画作りのセンスは、足を止めてもらえるかどうかに直結します。
→ 展示会向けであっても、一定のクオリティが求められることは忘れないようにしましょう。
展示会の動画は、「見てもらえない=存在しないのと同じ」です。
制作会社を選ぶ際は、“展示会という場における動画の機能”を理解しているかどうかを見極めることで、成果につながる動画制作につながります。
5. まとめ:展示会の成果を動画で最大化するために

展示会は、自社の製品・サービスに興味を持つ見込み顧客と直接出会える貴重な場です。だからこそ、ただ出展するだけでなく、「どうやって立ち止まってもらうか」「どうやって印象に残すか」が重要になります。
その中でも動画は、視覚的に強く訴求できる“最前線のツール”。
しかし、展示会という特殊な空間では「映像作品としての完成度」よりも、「どのように機能するか」が問われます。
本記事で紹介したように、展示会動画には次のようなポイントが求められます:
- 通行中でも目を引く「アイキャッチ性」
- ターゲットに刺さる情報を瞬時に伝える「情報整理力」
- ブースの会話を生み出す「接点づくり」
- 再生環境(無音・ループ)を考慮した設計
- ブース装飾とモニター位置の連動設計
これらをきちんと設計できれば、動画は単なる「賑やかし」ではなく、**展示会の成果を左右する“戦略的な武器”**になります。
そして、そうした動画をつくるためには、展示会という現場のリアルを理解した制作パートナーの存在が不可欠です。
企画段階からの相談、大歓迎です
私たちcaseでは、展示会向けの動画制作も数多く手がけており、「まずはどう活用すべきか?」という初期段階からのご相談にも対応しています。
- 展示会初出展なので、動画の役割から相談したい
- 展示会のテーマやブース設計に合った企画を提案してほしい
- 社内での意思決定がスムーズになるよう資料や構成案を整えてほしい
…といったお悩みにもお応えできます。
展示会で「来場者の印象に残る」動画を一緒に作っていきましょう。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。