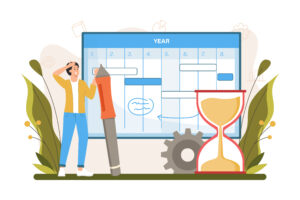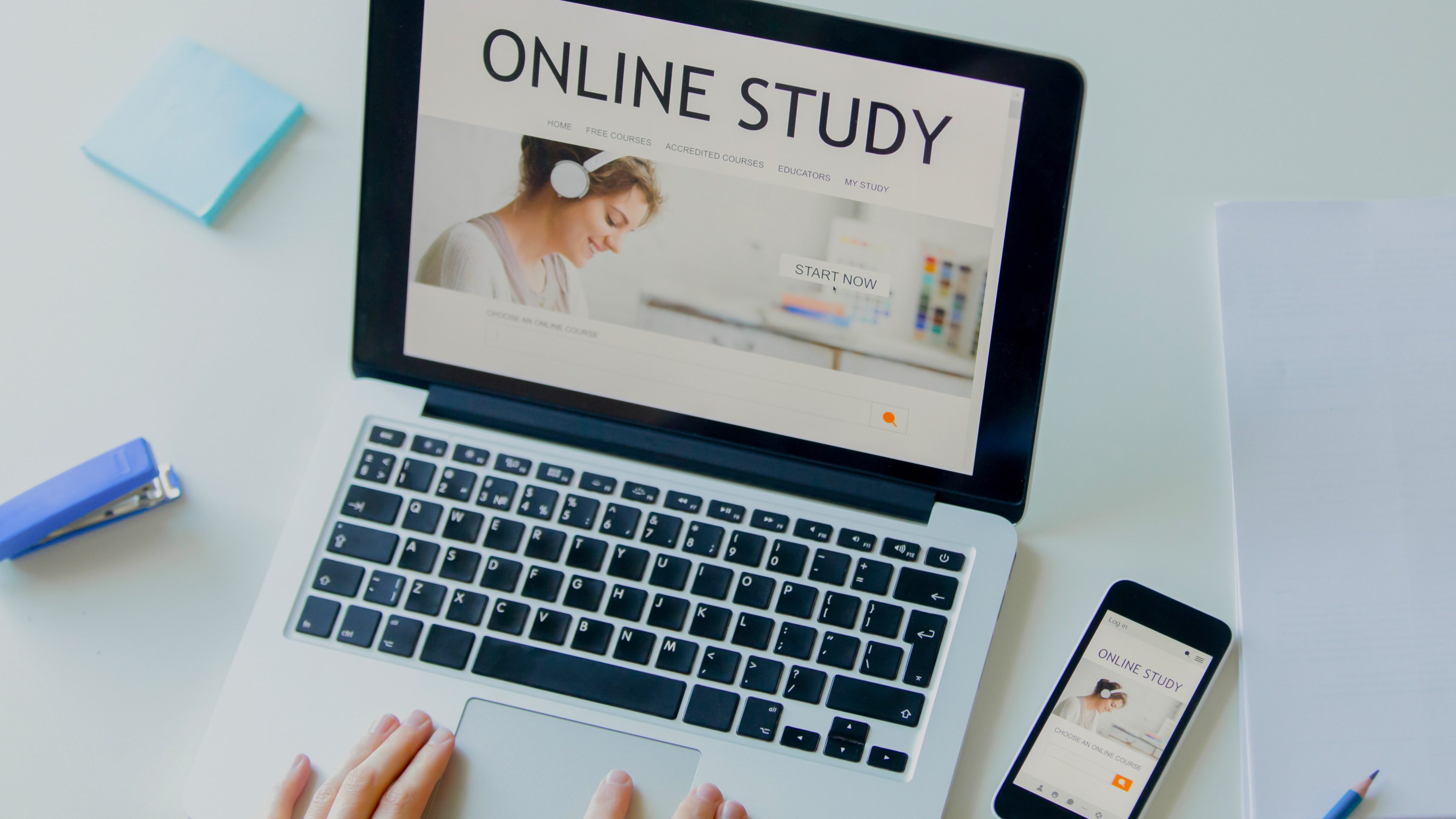動画制作は、「実際に編集されたモノ」をイメージしたりあるいは、そのイメージを共有することが難しいという特徴があります。
だからと言って、完成した状態を全くイメージできない…というのも制作進行上では大きな問題になります。
そのため、動画制作の際には「シナリオ・絵コンテ」と呼ばれる資料で関係者間で完成イメージを共有するというのが通常の流れです。
シナリオ・絵コンテについてよくあるQ&A
- シナリオ・絵コンテとはどのようなものですか?
-
シナリオは、動画の構成やその流れをテキストベースで記載したものです。絵コンテはシナリオが更に詳細なものになっており、絵や画像などを用いてできる限り完成に近いイメージと動画に入れられるナレーション/BGM/セリフなどが付加されたものです。
- シナリオ・絵コンテを制作するタイミングは?
-
ラフ、仮の状態のものであれば例えば発注前のタイミングで制作会社から提案される可能性もありますが正式なものは発注後に打ち合わせを重ねて「最終的な設計図」として提出されることが多いです。
- 発注前にシナリオや絵コンテで提案をもらうことは可能?
-
不可能ではありません。ただし、シナリオ/絵コンテを作成するにはとうぜん「コスト」が発生するため無料で依頼することはおすすめできません。数万円でもそのための費用を負担されることを前提に依頼されれば、多くの制作会社は対応してくれるはずです。
シナリオ・絵コンテとは
シナリオ
動画のストーリーや演者のセリフなどを文字で書き表したものです。
特に実写の映像でドラマ風のものや尺が長いものについては、全てを絵で表現するのに多大な労力がかかるため文字で細かくシチュエーションや人物について描写することでイメージを共有します。
ちなみに…辞書的な表現だと下記のようになるみたいです。
シナリオ(scenario)
1 映画・テレビなどの脚本。場面の構成や人物の動き・せりふなどを書き込んだもの。台本。
出典:コトバンク(https://kotobank.jp/word/%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%AA-4289)
絵コンテ
動画のシチュエーションや出演者・キャクターの動きを絵で表現したものです。
セリフや絵の表現だけでは伝わりにくい部分、ナレーションの文言については文字で補足することが多いです。
~1分くらいの短めの実写映像やモーショングラフィックスの動画などは本格的に撮影・制作に入る前に絵コンテを通してイメージを共有することが多いです。
こちらも辞書的な表現としては下記を参考ください。
【絵コンテ】映画・テレビドラマの制作に際し、各カットの画面構成を絵で示し、映像の流れをたどれるようにしたもの。
出典:コトバンク(https://kotobank.jp/word/%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%AA-4289)
シナリオ・絵コンテをチェックするポイント
チェックポイント①:イメージ通りかどうか
動画は基本的には「シナリオ・絵コンテ通り」に制作されます。
シナリオ・絵コンテを通してイメージを共有しているので当然なのですが、動画を制作するのに文字や絵をベースとしたものでイメージを共有するため、シナリオや絵コンテは「仮のもの」と認識されてしまい、後々「イメージと違う」とトラブルになることがあります。
繰り返しになりますが、動画は「シナリオ・絵コンテ通り」に制作されるということを念頭において自身がイメージしたものと乖離がないかを確認してください。
例としては、
- 動画のシチュエーション
- ストーリー
- 演者のセリフ回し
- ナレーションの原稿
- BGMのイメージ
さらにモーショングラフィックス動画の場合は
- ビジュアルのイメージ
- 動きのイメージ
などです。
チェックポイント②:must条件はクリアされているか
動画制作を依頼いただく際に、「必ずクリアしなければならない条件」があることがほとんどです。
それが、「商品を出さなければならない」とか「社員を登場させる」とかであればざっと目を通しただけでも確認できますが
- 商品や商標(ロゴなど)を動画の中に出す際の決まりごと(レギュレーション)をクリアしているかどうか
- 会社やブランドとしてその表現に問題はないか
- そもそも誤った表現がなされていないか
この辺りについては、入念な確認が必要です。
また担当者だけでは確認が難しいケースもありますのでかならず社内の担当部署や上長への確認を行った方が良いでしょう。
例えば、ナレーションの文言について表現そのものが誤っているのにナレーション収録時まで指摘がなくそのまま制作が進行してしまっていた…ということも稀にあります。
このケースだとナレーション収録時に気がついたため事故にはなりませんでしたが、収録完了後に発覚となるとスケジュール的にも費用的にも負担が増えるので、シナリオ・絵コンテ確認時にしっかりと確認しておきましょう。
チェックポイント③:発注者側で準備すべきものの有無
例えば自社製品のプロモーションの場合は発注者側で自社製品を手配して現場へ持ち込む必要があります。
また、限られた予算での制作の場合は撮影場所やキャスト、衣装なども発注者側の手配となるケースもありますので改めてシナリオ・絵コンテを確認する際に準備物の分担について確認しておきましょう。
撮影内容や、撮影対象物によっては予備として同じものを複数用意する必要があるケースもあるので「なにが、どれくらい必要なのか」について記載が無い場合は制作会社側に確認しておいた方が良いでしょう。
最後に
繰り返しになりますが、シナリオ・絵コンテ通りに制作が進むということを念頭において自身でしっかりと確認することは前提として、社内の関係各所へ確認とフィードバックを依頼しておきましょう。
動画制作についてのご相談は下記よりどうぞ。