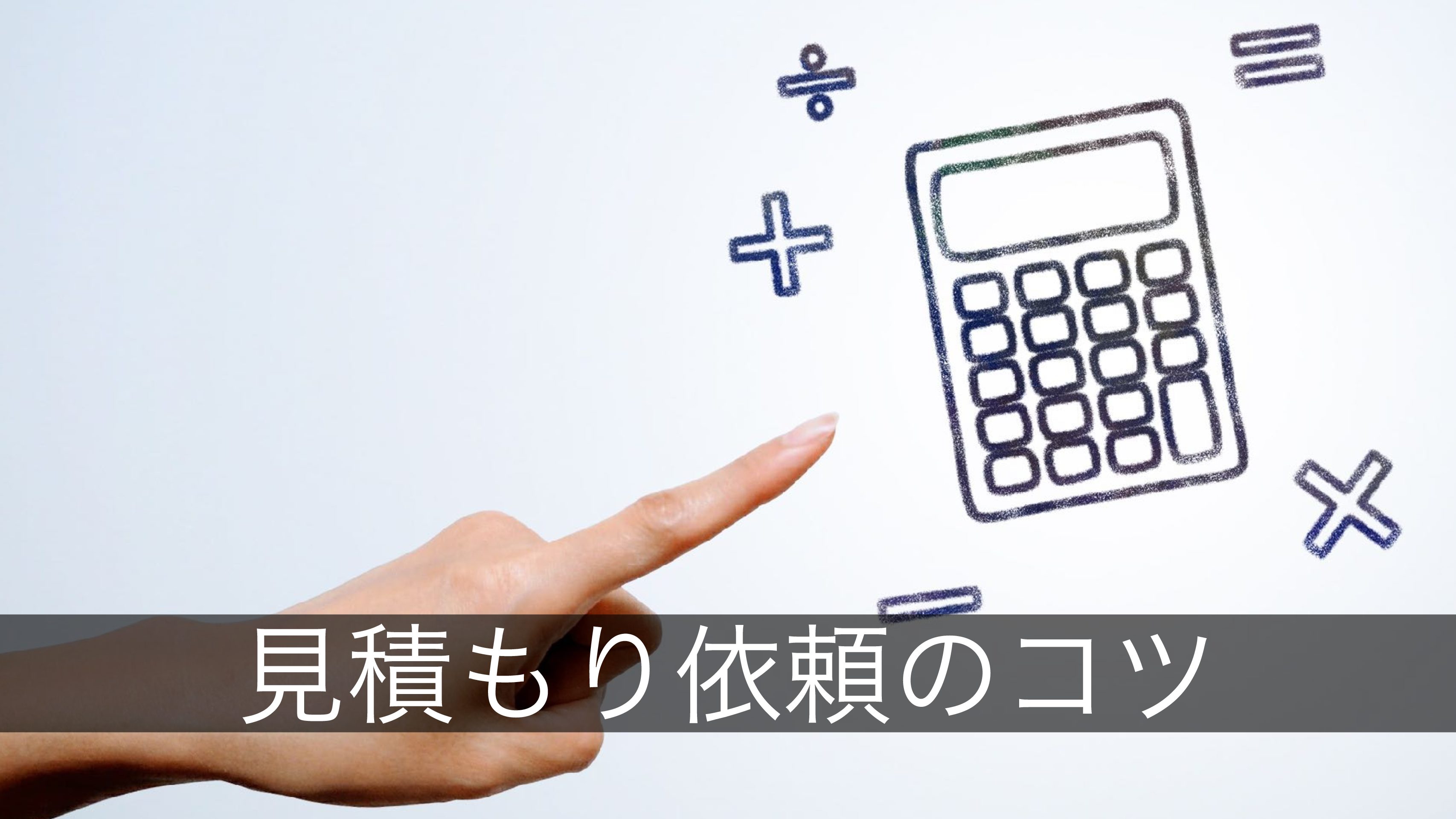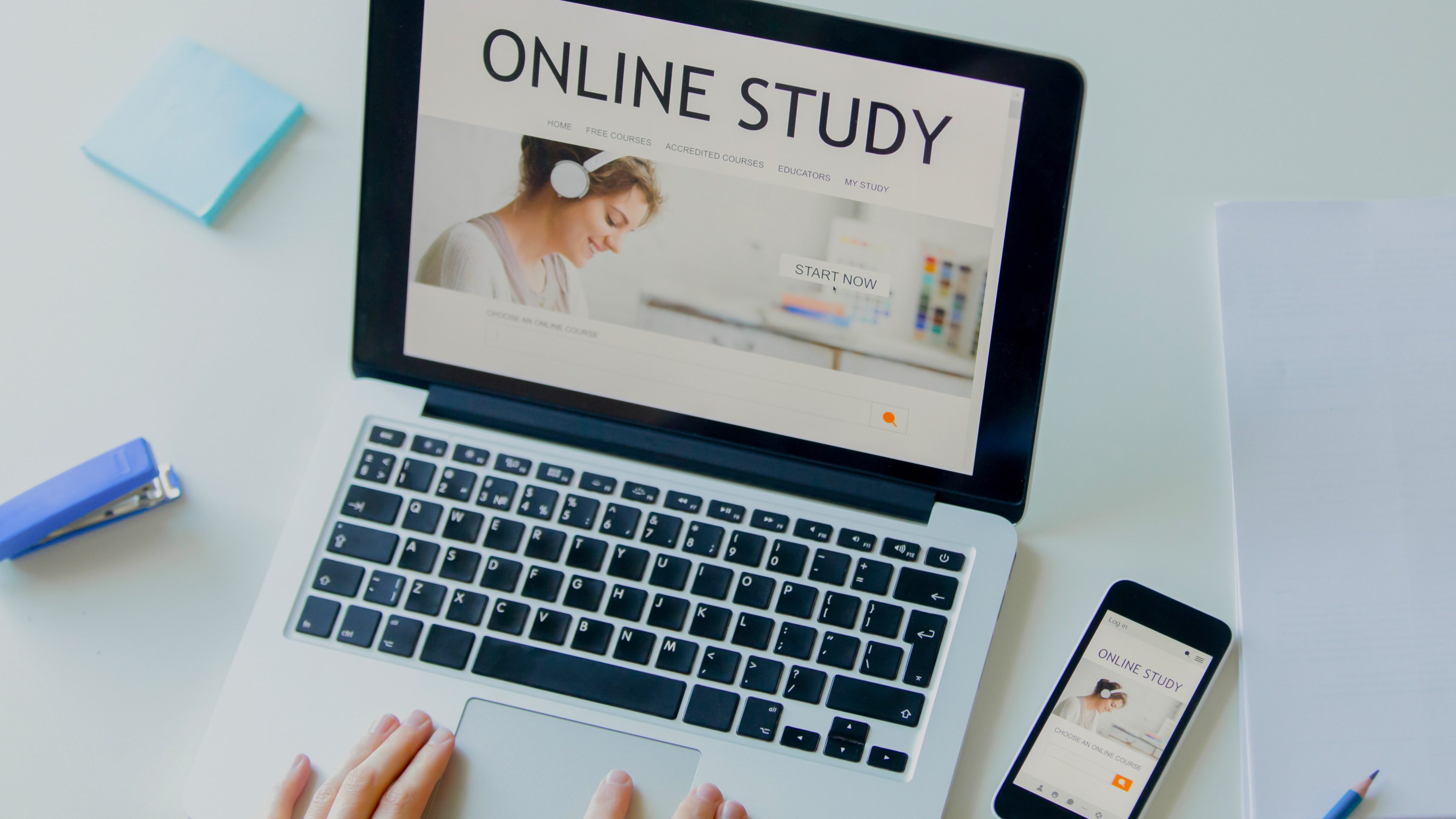動画制作を外注したい…と考えた時、おそらく多くの担当者の頭に浮かぶのは
「動画制作ってどれくらいの予算が必要なんだろう…?」ということではないでしょうか。
普段動画制作に携わることのない人にとって、動画制作費というのは
なかなかイメージしにくいものだと思います。
動画制作費は突き詰めると制作会社ごとの、あるいは実際に稼働するクリエイターごとの
単価や人件費、利益率の設定によって変わってしまうため明言できません。
なので、このページでは動画制作の費用を知る際に必要となる
「動画制作の見積り」を依頼するコツについてポイントを整理して解説します。
なぜ、同じ相談内容で見積り金額が大きく異なるのか?
理由は大きく3つで、
- 制作会社ごとに前提としている制作条件が異なる
- 制作会社ごとに設定されている原価率が異なる
- イレギュラーへの対応費用を想定しているか否か
のいずれかであることが多いです。
1つずつ解説します。
制作会社ごとに前提としている制作条件が異なる
同じ動画をイメージに近いサンプルとして複数の制作会社に提示したのに、見積りの金額が大きく異なる…ということもあると思います。確かに、お客様の目線で考えるとなぜそのようなことが起きるのか不思議だと思います。
しかし、同じ動画を見たとしてもそれをもとに見積りをする際に「想定する制作条件」は制作会社によって違いがでるというのは当たり前に起きてしまうことです。
特に違いが出やすいのは下記の3つのポイントです。
- 撮影日数
- 出演者・撮影場所の手配の有無
- 照明の有無
撮影日数
「撮影日数」などは金額が大きく変わるポイントの1つです。提示されたような動画を制作する際に、撮影が1日で問題ないのか?2日間必要なのか。外での撮影の場合は予備日の確保が必要なのかなど、どのように想定するかによって大きく変動します。
出演者・撮影場所の手配の有無
「出演者」の手配の有無も大きなポイントです。例えば自社の社員が出演する場合には、出演者の手配は発注側の企業の役割になりますが、役者やモデルを制作会社側が手配する際には
- キャスティング費(キャスティング会社に候補を出してもらう費用)※不要なケースもある
- 出演費(モデル・役者や、所属事務所に支払う費用)
- 衣装
- メイク・ヘアメイク
などの費用が加算されます。
また、撮影場所も同じように大きく金額が変わるポイントです。動画の撮影のためにスタジオなどを借りると安くても10万円、高い場所になると50万円を超える費用がかかる場所もあります。
照明の有無
動画制作に慣れていないと、その動画に「照明」が使われているかどうかを判断するのは難しいかもしれません。しかし、照明があるのと無いのとではやはり大きく金額が変わります。
具体的には、
- 照明スタッフの人件費
- 照明機材費
- 人と機材を運ぶ車両費
- 照明をセット・撤去するために必要な時間分の他のスタッフの人件費、ロケーション費
など、照明機材を使うことで必要な費用は機材や照明スタッフの人件費だけではないというのがポイントです。
また、照明機材もどの程度の機材をどれくらい使うのかによって費用が大きく変わる、見積り金額の変動ポイントとなります。
制作会社ごとに設定されている原価率が異なる
この点はタイトルの通りになるのですが、制作会社によってお客様からいただく予算のうちどれくらいの割合を原価として使えるのか。(=粗利をどれくらい残す必要があるのか)が決まっています。
筆者の経験上、制作会社ごとにそこまで大きな違いは無いのですが、傾向としては小規模な制作会社のほうが原価率が高い(粗利率が低い)傾向にあると言えるでしょう。
また、原価率は制作予算の規模によっても異なります。例えば、〜300万円くらいまでの予算規模であれば45〜50%程度の原価率だとすると、1000万円以上の案件となると30〜40%程度の原価率などです。
イレギュラーへの対応費用を想定しているか否か
基本的に「想定していない」ということはないはずですが、見積りをシビアに比較されるケースや予算が相当にキツいケース等の場合は「少しでも想定外のことが起きたらアウトだな」という見積りを出す可能性はゼロとは言えません。
通常は「制作費」「雑費」などの項目で制作費全体の10〜15%程度の費用を確保し、イレギュラー対応の余白を残しておくのですがこの点についてはお客様へ説明しても理解してもらうことが難しいケースもあるため、各社で対応がわかれるところです。
見積りを依頼する際のコツ
①イメージに近い動画を提示する
見積りを依頼する際に大事なのは「自分がイメージしている動画に近い事例」を
見積り依頼時に提示することです。
「こんな感じの動画制作を依頼した場合、いくらくらいかかりますか?」
と問い合わせると、あなたのイメージする動画を制作する際に必要になる費用を
大まかにつかむことができるでしょう。
「大まかに」というのは全く同じ制作条件でも制作費用というのは、制作会社やその他の要件によって変動するためです。
細かい条件を制作会社と詰めるまでは、あくまでも「概算」としての見積りである可能性が高いので
その点は理解しておいた方が良いでしょう。
それでもできる限り詳細な制作費を知りたいときには、そのイメージに近い動画のどの部分が最も自分のイメージと
重なるのかを伝えましょう。
さらに、
- キャスト(出演者)
- ロケーション(撮影場所)
などの手配を自社で担当するのか、制作会社に任せたいのかなど細かな部分なども
こちらの記事を参考に伝えてみましょう。

②一定の幅のある予算と、制作したい動画についての情報を提示する
「どんな動画が良いのか全くイメージがつかない…」という場合は
例えば「インタビュー動画が作りたい」とか、
「いわゆる会社紹介っぽいのって上司からは言われてるんだよなぁ」とか
それくらいの情報があれば、
「50万〜100万円で制作可能なインタビュー動画の事例(実績)を教えてください」
「100万〜200万円で制作可能な会社紹介動画の事例(実績)を教えてください」
という依頼でもOKです。
上記のような依頼であれば、おそらく各社から3〜4本程度の実績が送られてくるはずです。
その中からイメージに近い動画をピックアップし、さらにその動画を事例として1の「イメージに近い動画を提示する」を
実行することで制作予算の把握が可能になります。
多少手間ではありますが、自分で「動画を探すのがめんどくさい」or「イメージがつかない」という場合はこの方法を試してみてください。
③予算と作りたい動画事例を同時に提示する
見積りをとる…という趣旨からは少しそれてしまいますがこれができるとベストです。
どちらかというと、見積りをとるというよりは制作パートナーを決める際の方法とも
言えるのですがこの方法が最もコスパの良い制作ができる可能性が高まります。
理由は、以下の通りです。
・制作会社側に「この会社は本当に動画を作る気がある」と思ってもらえる
・「確度の高いお客さん」なので金額面で頑張ってもらえる可能性が高い
・「確度の高いお客さん」なので、予算内で制作する方法を模索してくれる
ただし、提示した事例に対して予算が高すぎる場合はリスクでもあります。
敢えて提示された予算よりも安く制作したいという制作会社はありません。
この方法で進める場合は提示する事例と予算のバランスをある程度見極められる自信がある場合に限った方が良いでしょう。
④すぐに使える「見積り依頼メール」の雛形
件名:動画制作の概算見積のご相談(会社紹介/60〜90秒/実写)
本文:
◯◯株式会社 ◯◯様
お世話になっております。△△株式会社の□□です。
下記条件で概算見積をご提示いただけますでしょうか。
【背景・目的】展示会でのループ再生/採用サイトの一次利用
【参考動画URL】https://(2〜3本)
【方式】実写(インタビュー+B-roll)
【本数・尺】1本/60–90秒
【撮影】1日/都内1拠点(社内で出演者手配)
【納期目安】初稿◯営業日、修正2回
【承認体制】担当1名/決裁1名(計2名)
【納品仕様】横16:9/字幕付き/SNS尺違い(15秒)も見積内訳で
【予算感】100–150万円の範囲で最適案をご提案ください
【その他】NDA即日対応可、電子契約希望
内訳(人件費/機材/編集/交通・実費)と前提条件の明記をお願いします。
何卒よろしくお願いいたします。
動画制作の見積りについてよくあるQ&A
- なぜ、同じ相談内容で見積り金額が大きく異なるの?
-
理由は大きく2つです。1つは前提としている制作条件が異なる可能性があります。例えば照明の有無やスタッフの人数などは制作会社側の想定で見積るため、違いがでます。2つ目は会社ごとに設定している粗利率や原価に由来するものです。
- 見積り書のなかで注意するべきポイントは?
-
制作内容によって異なりますが、「撮影日数」「想定スタッフの数」「著作権or納品物の利用範囲」「想定しているクリエイティブサンプルの有無」の4つは特に注意して確認・比較する必要があります。
- 精度の高い見積り書をもらうコツは?
-
「イメージに近い動画と想定している予算」の2つを用意して、「撮影日数」「出演者手配の有無」「撮影場所の手配の有無」の3つの情報を伝えた上で、見積り依頼することです。
- 見積りの取り方は?
-
見積りは、同条件での比較ができる要件セットを明文化して依頼する。最低でも**背景/目的、参考動画URL(2〜3本)、制作方式(実写/モーショングラフィックス)、本数・尺、撮影日数・拠点、初稿目安、修正回数、承認者数、納品仕様(縦横・字幕・尺違い)**を記載し、内訳と前提の明記を求める。
- 見積りの取り方のポイントは?
-
ポイントは前提の共通化×内訳の可視化。本数・尺・撮影日数・修正回数・承認者数・初稿目安を数値で固定し、人件費/機材費/編集費/交通・実費など費目と含有作業の範囲を書面で揃える。こうすると後の追加費・納期ブレを抑えられる。
- 見積りをもらう際のチェックリストは?
-
①前提:本数×尺、納期(初稿◯営業日)、修正回数(初稿+◯回)、撮影日数・拠点、承認者数。②方式・体制:実写/モーショングラフィックス、内製/下請け、担当ディレクター/プロデューサー。③法務:NDA、出演同意、ロゴ・フォント・BGM・素材ライセンス、ロケ許可。④納品:縦横、字幕、尺違い、データ形式。以上を見積り本文に明記させる。
- 見積りの取り方の注意点は?
-
抽象的な依頼文だけで送らない(参考動画・数値前提・使用範囲が無い)。ライセンス・許諾類(BGM/素材/ロゴ・商標、出演同意、NDA)の有無を曖昧にしない。変更管理(受付窓口・記録様式・費用/納期影響の算定)と検収基準・短納期割増を事前に取り決める。
- 見積りを比較するポイントは?
-
比較はまず前提の揃え直し(本数・尺・撮影日数・修正回数・承認者数・初稿目安)を行い、費目×範囲で含む/含まないを照合する。1本あたり/1分あたり単価と日当換算、ロケ・スタジオ・機材・MG・ナレーション・字幕・予備日の扱いを横並びにして、同条件での再現可否まで見比べる。
- 見積りを比較する際の注意点は?
-
総額の安さだけで判断しない。注記の「含まない」(スタジオ・照明・ヘアメイク・交通・テロップ・ナレーション・多言語字幕)が多い見積りは後から上振れしがち。BGM/素材のライセンス条件(媒体・期間)、尺違い・縦横派生、キャンセル料/支払サイト、変更管理条項まで読み込み、検収基準が明確かを確認する。
- 無料見積りの範囲は?
-
無料見積りの範囲は、具体的にはヒアリング(30〜60分目安)と要件整理、そして概算/正式見積りの作成まで。前提セット(本数・尺・撮影日数・修正回数・承認者数・初稿目安・納品仕様[縦横/字幕/尺違い]・使用範囲)に基づき、費目ごとの内訳と「含む/含まない」を明記し、再見積りは1〜2回までが一般的。構成案・絵コンテ・ロケハン・テスト編集(モーションテスト)・キャスティング打診・複数案の並行提示・短納期の先行着手は有償に切り替わることが多い。
最後に
当然ながら制作会社もビジネスとして動画制作を行なっているので、「とりあえず見積りとろう」という感じのお客さんよりも、
「制作することは決まってるから制作会社を探さなきゃ…」というお客さんの方がどうしても手厚い対応になります。
今回紹介したのは、「とりあえず見積りとろう」という状態でもそれなりにしっかりと制作会社側に対応してもらうためのコツと言ってもいいかもしれません。
今回紹介した方法を参考にしていただきつつ可能な範囲で準備をしてから、制作会社に見積りを依頼してみましょう。