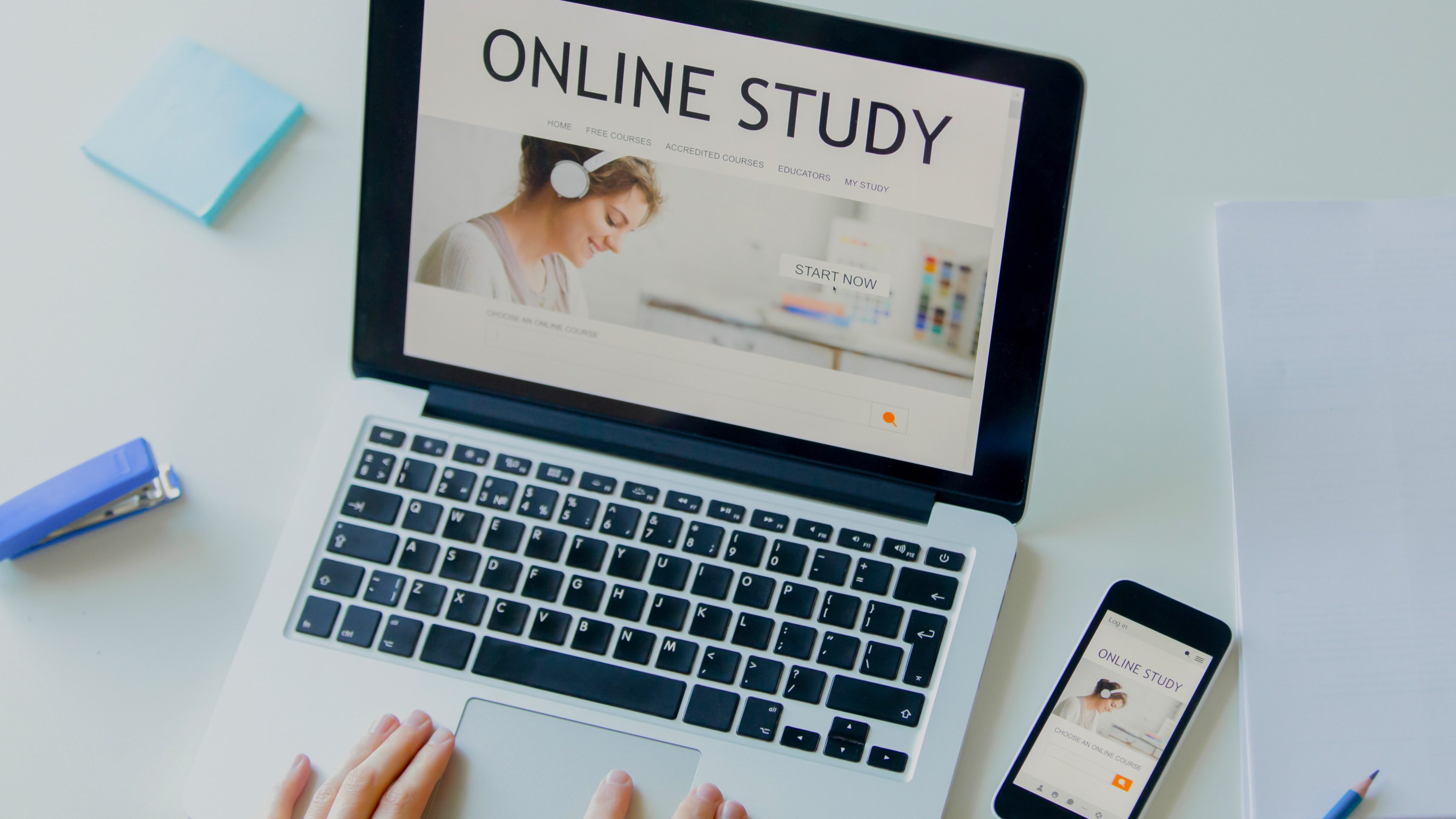「モーショングラフィックス動画を制作したいが、何から準備すればよいかわからない」「制作会社に依頼するときに押さえるべきポイントを知りたい」——マーケティング・広報・採用・展示会担当者にとって、外注制作の準備は迷いどころが多いテーマです。発注者として決めるべきこと、確認すべきことを理解しておけば、制作会社とのやり取りがスムーズになり、成果に直結します。
この記事では、予算30万〜200万円超でモーショングラフィックス動画を外注するケースを想定し、発注者が知っておくべき情報設計、制作期間の目安、役割分担、チェックポイントなどを解説します。
この記事の要点
- 目的とKPIを明確にする:完全視聴率、展示会での滞在時間、認知度、採用応募数など、動画で達成したい指標を初めに決める
- 仕様と制約を企画段階で確定:尺(15〜30秒/60〜90秒)、アスペクト比(16:9・9:16・1:1)、解像度(FHD・4K)、フレームレート(30fps・60fps)、無音/ループ再生の有無を最初に定義
- ブランド整合性を担保する:ロゴ・カラー・フォント・レイアウトなどのガイドラインを準備し、スタイルフレームの段階で確認する
- 制作期間と役割を把握:標準7〜8週、短納期5〜6週、特急4週モデルの違いを理解し、RACI表とレビューSLAを設定する
- 権利と品質チェック:ナレーション・BGM・フォントのライセンス、利用範囲を確認し、納品前に技術テストと実機確認を行う
- 予算に応じた戦略:30〜60万は素材活用とテンプレ活用中心、80〜150万はオリジナル制作、150万以上は世界観構築と多言語展開を想定する
- 発注チェックリストで漏れを防ぐ:目的・視聴環境・仕様・権利・修正回数・納期・担当窓口などを網羅したリストを使い、契約前に確認する
モーショングラフィックス動画制作時の目的とKPIを決める

動画制作会社へのブリーフィングの第一歩は「なぜこの動画を作るのか」を数値や、具体的な説明で表すことです。例えば、Webサイトのコンバージョン率を15%向上させる、展示会ブースの滞在時間を平均1分から3分に伸ばす、指名検索数を30%増やす、採用応募数を25%増やす、といった具体的なKPIを設定すること。
加えて、それらのKPIを達成するために「動画でアテンションする」「サービス名を覚えてもらう」「業務内容の理解を促す」など、動画の役割を明確にすることも非常に重要です。
目的や動画の役割が明確であれば、制作会社は構成や演出の優先順位を付けやすく、成果が測定しやすくなります。
企画段階で確定すべき技術仕様
動画の仕様変更は制作工数と費用に直結するため、次の項目を企画段階で固めておくことが重要です。
特に尺以外の部分は、特別な指定がない場合には一般的な仕様での制作という認識で進むこともあるので、指定がある場合には注意が必要です。
| 項目 | 推奨設定 | 発注時のポイント |
|---|---|---|
| 尺 | 展示会:15〜30秒 Web:60〜90秒 | 用途に応じた長さにし、長尺では情報の優先順位を決めて構成する |
| アスペクト比 | 16:9(横)/9:16(縦)/1:1(正方形) | 配信媒体やモニターの仕様に合わせる。縦横併用ならセーフエリアを意識したレイアウトを初期設計に盛り込む |
| 解像度 | FHD(1920×1080)/4K(3840×2160) | 4Kは高精細だが制作費とデータ容量が増える。使用場所や予算に応じて選択する |
| フレームレート | 30fps(標準)/60fps(滑らか) | 動きの滑らかさとデータ容量のバランスを考慮。特殊演出がなければ30fpsで十分 |
| 音声・ループ | あり/なし/選択可能 ループ対応の可否 | 展示会やサイネージは無音・ループが基本。WebやSNSでは音声と字幕の有無を事前に決めておく |
ブランド整合性を担保する
動画を制作するに当たって、自社のブランドガイドラインを遵守する必要がある場合には、ロゴデータ、カラーコード、フォント名、レイアウト基準などのブランドガイドラインを事前に準備して、制作会社に連携しましょう。
また、スタイルフレーム(style frame:静止画のデザイン例)を制作会社から受け取ったら、以下の観点で確認します。
- タイポグラフィ:既存ブランドフォントを使用し、可読性を確保。ゴシック体は視認性重視、明朝体は高級感演出など意図を明確にする
- 色彩設計:ブランドカラーを適切に使用し、背景と文字のコントラスト比4.5:1以上を目指す
- 余白とレイアウト:統一したグリッドシステムを採用し、情報の優先順位が一目で分かるように設計する
- アイコン・イラスト:同じ線幅・サイズ・スタイルで統一し、拡大縮小しても見栄えが崩れないか確認する
モーショングラフィックス動画制作時の制作期間と役割分担

制作期間は動画の内容や体制によって変わりますが、モーショングラフィックス動画では大まかに以下の3モデルが想定されます。発注側は、いつ誰がどの工程に関わり、どの段階で承認が必要かを理解しておきましょう。
| モデル | 期間 | 修正回数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 標準モデル | 7〜8週間 | 2〜3回 | 企画から納品までじっくり進行し、品質を重視 |
| 短納期モデル | 5〜6週間 | 1〜2回 | 工程を並行して進めるため修正回数や検討時間を減らす必要あり |
| 特急モデル | 4週間 | 1回 | 既存素材活用やテンプレート使用が前提。大幅な演出は不可 |
各モデルで発注者が担う主な役割は次のとおりです。
- 担当者(R):制作会社との窓口となり、企画段階の要件定義や素材提供、進行管理を行う
- 決裁者(A):要件定義・構成案・スタイルフレーム・最終納品の承認を行い、仕様変更や予算追加などの重要な判断を担当する
- 協力者(C):社内の関係部署(ブランド担当・製品担当など)から必要な情報や素材を提供し、内容の適正を確認する
- 報告先(I):最終成果物や進行状況を共有するだけの立場。関与度は低いが、情報共有のために連絡網に含める
レビュー運用では、各段階の承認期限を明確にしたSLA(サービスレベル合意)を設定します。例えば「初稿のフィードバックは受領後48時間以内」「修正は2回まで」といったルールを事前に合意するとスケジュールの遅延を防げます。また、承認者が長期不在の場合に備えて代理承認者を決めておきましょう。
企画〜プリプロ(制作準備)段階のチェックポイント
要件定義が曖昧だと後工程での修正が増え、費用と納期に影響します。次のチェックリストを活用し、制作会社に共有するブリーフィング資料を作成してください。
- 目的・KPI:動画の目的と測定指標(数値目標)を明示する
- ターゲット:想定視聴者の属性(年齢層、職種、興味関心など)
- メッセージ:最も伝えたいポイント
- 尺:最大・最小を決め、情報密度を調整する
- 納期:最終納品日と中間レビューの期日
- 媒体:Web、SNS、展示会、サイネージなど配信先
- 利用範囲:期間(例:1年間)、地域(国内・海外)、媒体の制限
- 素材準備:ロゴデータ、写真・映像素材、製品3Dデータ、ブランドガイドラインなど支給可能な素材
モーショングラフィックス動画の制作期間と承認フロー

一般的なモーショングラフィックス動画の制作工程は次の通りです。発注側は各工程での確認ポイントと役割を把握しておきます。
| 工程 | 主な作業 | 発注者の役割 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 要件定義 | 目的・KPI・視聴環境の確認、素材収集 | 担当者が制作会社へブリーフィングし、決裁者は目標を承認する | 約1週間 |
| 企画・構成 | シナリオ作成、絵コンテ制作 | 初稿の確認とフィードバック、方向性の確定 | 1〜2週間 |
| デザイン | スタイルフレーム作成、アセットデザイン | ブランド整合性のチェックと承認 | 1〜2週間 |
| アニメーション | モーション制作、ラフから本制作へ | ラフアニメーションの確認と修正指示 | 2〜3週間 |
| 音響・整音 | ナレーション・BGMの手配と整音、字幕制作 | 原稿提供、ナレーター選定、ライセンス確認 | 約1週間 |
| 仕上げ・納品 | 最終調整、書き出し、実機テスト | 検収、承認、バックアップの受領 | 数日〜1週間 |
これらの要件は動画の視聴環境によっては非常に重要になります。
例えば、展示会やサイネージで使う場合は無音でも理解できるようテロップやグラフィックスで情報を補う構成にする必要があります。また、ループ再生に対応するため、動画の最後と最初を自然につなげる編集が必須です。3〜5メートル離れても読める文字サイズ(目安24pt以上)を採用し、長尺のテロップは分割するなどの配慮が必要になります。
権利関係と技術チェック
ライセンスの不備や仕様ミスは後から大きな問題になるため、発注段階で次の点を確認します。
技術的な設定については、動画を配信する媒体で特別な指定がなければ、基本的には気にする必要はありませんが、
特殊な配信・視聴環境の場合には事前に確認しておきましょう。
- ナレーション:外部ナレーターを起用する場合は権利譲渡契約を締結し、二次利用の範囲を明記する
- BGM・効果音:著作権フリー素材でも利用範囲(商用利用可否、期間)を確認し、ライセンス情報を制作会社から提出してもらう
- フォント:商用利用ライセンスを確認し、埋め込み権限の有無を確かめる
- 利用範囲:動画の使用期間・媒体・地域を契約書に明記し、超過する場合の追加費用を決めておく
- 実機テスト:展示会やサイネージで実際に再生し、ループ再生・無音再生・明るさなどを確認する
モーショングラフィックス動画制作時の予算と制作戦略
予算に応じて制作の範囲や求めるクオリティが変わります。発注側は目的とのバランスを考え、どこに投資するかを決めましょう。
30〜60万円:効率重視モデル
- 素材活用:既存写真・ロゴ・アセットを最大限に使い、素材購入費を抑える
- テンプレート活用:汎用テンプレートや既成のモーションを使用して制作コストと期間を削減する
- シンプル演出:複雑なアニメーションや3D表現は避け、情報の伝達を優先する
80〜120万円:バランス重視モデル
- オリジナル制作:専用イラストやアイコン、オリジナルのモーショングラフィックスを制作する
- 演出最適化:ブランドに沿ったカスタムアニメーションやインフォグラフィックを取り入れる
- 音響強化:プロのナレーターとオリジナルBGMを導入し、印象を高める
150万円〜:世界観構築モデル
- 世界観構築:独自のビジュアルスタイルをゼロから設計し、ブランデッドムービーとしての価値を高める
- 高度モーション:3Dアニメーションや複雑なエフェクトを活用し、没入感を演出する
- 多言語展開:字幕やナレーションの多言語対応を施し、海外市場にも拡張する
【コピペOK】発注チェックリスト
- 目的・KPI:動画で達成したい具体的な成果と評価方法
- 想定視聴環境:Web、SNS、展示会、サイネージなど
- 尺:秒数の上限・下限を設定する
- アスペクト比:16:9/9:16/1:1 など
- 解像度:FHD/4K
- フレームレート:30fps/60fps
- 音声:あり・なし・選択可能
- 字幕:必要・不要
- ループ対応:必要・不要
- 納期:最終納品日と中間マイルストーン
- 修正回数:含まれる回数と追加費用
- 権利関係:著作権の帰属・利用範囲
- 利用範囲:使用期間・地域・媒体
- 納品形式:MP4/MOV/その他
- バックアップ:プロジェクトファイルの保管有無
- 担当窓口:連絡先と承認フローを明確にする
モーショングラフィックス動画の制作をご検討でしたら、お気軽にご相談くださいませ。
よくある質問
- Webと展示会で同じ動画を使い回せますか?
-
基本構成は共通化できますが、音声の有無・文字サイズ・ループ設計が異なるため、比率や尺、テロップ密度を調整した派生版を制作することを推奨します。展示会向けは無音・ループ仕様、Web向けは音声あり/字幕ありを想定すると良いでしょう。
- 社内承認が多くて進みません。何から手を打つべきですか?
-
初回打ち合わせでRACI(役割分担)とレビューSLA(48時間)を合意し、決裁者の事前確保と差し戻し基準(軽微・中・大)を文書化します。レビュー期限を明確にすることで承認滞留が減ります。
- 制作途中でアスペクト比を変更したい場合は?
-
デザイン以降で比率を変えると工数が大幅に増えるため、企画〜デザイン段階で決めるのが理想です。縦横併用が必要な場合は、セーフエリアを考慮したレイアウトを初期設計に組み込みましょう。
- データ納品時の推奨仕様は?
-
配信用は「H.264 MP4 / 1080p / 29.97fps / 15〜25 Mbps」が一般的です。ただし、配信先で特段の指定がない場合(Youtubeでの配信など)は、あまり気にする必要はありません。
- 短納期でも品質を落とさず制作できますか?
-
可能ですが、事前準備と効率的な進行管理が必須です。素材準備、決裁者の限定、修正回数の制限を前提に、短納期モデルで5〜6週間、特急モデルで4週間まで圧縮できます。10〜20%の割増費用が発生する場合があります。
関連記事